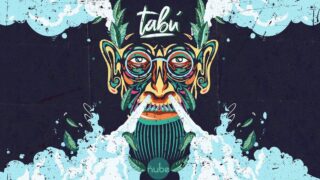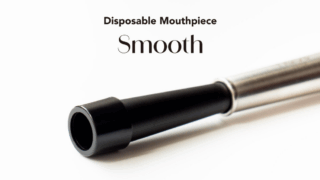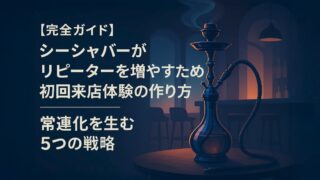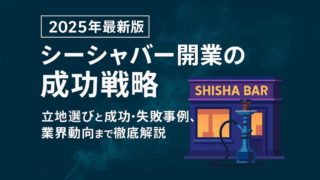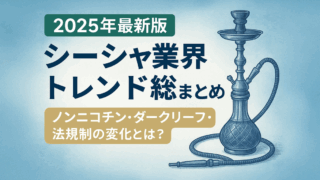シーシャ(別名:水タバコ)は、ここ数年で“おしゃれ”や“チル”の象徴として若者文化の中に浸透してきました。
しかし、2025年現在、業界は一つの岐路に立っています。
人気はある――けれど、実際の利用者は思ったほど多くない。
Z世代(大学生層)の86%が「一度も利用したことがない」という衝撃的なデータがそれを物語っています。(出典:RECCOO調査 2025年6月)
本記事では、シーシャ業界の現状・トレンド・課題、そしてZ世代に響く“新しい体験設計”について徹底的に分析します。
シーシャカフェを運営する方や、これから参入を考える方にとって、“未来を生き残るためのヒント”をお届けします。
日本と海外におけるシーシャカルチャーの現在地
日本では急増・淘汰期に突入するシーシャカフェ
ここ5〜6年、日本ではシーシャカフェやラウンジが急増しました。
特に東京・大阪・福岡などの都市部では、内装にこだわった店舗やSNS映えを意識した店が乱立。しかし今、供給過多による淘汰の波が押し寄せています。
「チル文化」ブームの裏で、競争の激化と収益性の低下が進行中です。
海外では“ウェルネス・カルチャー”と融合する流れ
一方、ドバイやロンドン、ベルリンなどでは、シーシャが“リラクゼーション体験”として再定義されています。
特に中東ではハーブベースやフルーツフレーバーを中心に、“健康的な社交文化”として根付いています。
この差は、単なる嗜好品としてではなく「ライフスタイル体験」として設計されているかどうかにあります。
Z世代とシーシャのリアルな関係性:データで見る現実
利用率わずか14%:ブームと実態のギャップ
SNSでは「チル」「映え」「おしゃれ」といった言葉とともに、シーシャを楽しむ投稿が数多く見られます。
しかし、実際のデータは意外にも冷静です。
株式会社RECCOO(2025年6月実施)の調査によると、Z世代(大学生層)の約86%が「一度もシーシャを利用したことがない」と回答。
つまり、Z世代の中でシーシャを「体験したことがある」層は、たった14%にとどまっています。
「ブーム」という言葉の裏には、SNS上の“話題の錯覚”と実際の利用者層の乖離が存在します。
「健康リスクが怖い」85%の声と、その背景心理
同調査では、「健康リスクがあるなら利用したくない」と答えた学生が85%にのぼりました。
タバコ=有害という認識が強い中で、シーシャも“喫煙の一種”として敬遠されがちです。
特に非喫煙者や女性層では、「喉が痛くなりそう」「煙が苦手」「体に悪そう」という心理的なハードルが高い。
これはZ世代が重視する「ウェルネス」「自己管理」「クリーンなイメージ」と正面からぶつかるポイントです。
“映え”と“チル”が生む矛盾:Z世代の価値観を読む
興味深いのは、「シーシャの印象」を尋ねた際の回答。
31%が「おしゃれ・映えスポット」と回答しており、ビジュアル的魅力は一定の評価を得ています。
一方で、23%が「体に悪い」と回答し、最も多かったのは「興味がない」という冷めた反応でした。
つまりZ世代にとって、シーシャは“魅力的だけど、自分ごとではない”存在。
この距離をどう縮めるかが、今後のシーシャカフェ経営の最大の課題です。
シーシャ業界の構造変化と課題
供給過多・競争激化と淘汰の波
2019〜2023年にかけて、シーシャカフェ・ラウンジは全国的に急増しました。
その結果、2025年現在は過剰供給による淘汰期に入っています。
家賃・人件費・炭やフレーバーなどの原価が上昇する一方で、価格競争が進み、利益率が急落。
生き残る店舗は、「差別化・体験設計・コミュニティ化」を実現できているかどうかで明暗が分かれています。
コスト高と法規制:経営リスクの二重構造
シーシャは法的に「喫煙目的施設」として扱われるケースが多く、未成年入店禁止・換気・防火・煙管理といった規制に常に注意を払う必要があります。
特に都心では、近隣住民からの苦情対応も課題。
さらに、高級ラウンジ型店舗では初期投資1,000万円超も珍しくなく、“オシャレ空間”をつくるほど、維持コストが重くのしかかります。
“体験+付加価値”で生き残る店舗の共通点
淘汰を生き延びた店舗に共通するのは、次の3つの要素です:
- 香り×空間の没入体験
→ 照明・音楽・香りを連動させ、五感で“チル”を感じさせる演出。 - 非喫煙者への配慮
→ ノンニコチンやハーブ系フレーバーを導入し、健康志向層を取り込む。 - SNS拡散前提の設計
→ 写真映えするガラスボトル・照明・内装で、UGC(ユーザー投稿)を誘発。
これらは単なる“喫煙体験”ではなく、“空間を味わう嗜好品”へと進化するための鍵です。
トレンド分析:ノンニコチン・複合体験型ラウンジの台頭
健康意識に寄り添う“ノンニコチン・ハーブベース”戦略
Z世代が最も求めているのは「安心してチルできる場所」。
そのニーズに応える形で、ノンニコチン・ハーブベースの代替シーシャが急速に普及しています。
香りのバリエーションも豊富で、フルーツ系・ティー系・スパイス系など、喫煙経験がない人でも「香りを味わう体験」として楽しめる点が支持されています。
この動きは、健康懸念を緩和するだけでなく、“ウェルネス文化”への接続点としても有効です。
音楽・アート・スイーツの融合がつくる“新チル文化”
シーシャ単体ではなく、音楽・アート・スイーツとの融合が新たな価値を生み出しています。
たとえば、新宿のMarble Shisha Loungeでは、香りとデザート、照明演出を組み合わせた「五感チル空間」を展開。
SNSでは「デートで行きたい」「癒される」といった投稿が多く、Z世代女性を中心に支持を集めています。
こうした“体験融合型”店舗は、来店体験=ブランディング体験として成立している点が強みです。
SNS設計で拡散を狙う“フォトジェニック戦略”
いまやZ世代の来店動機の多くは「インスタで見た」「友達がストーリーに上げていた」。
つまり、UGC(ユーザー生成コンテンツ)による集客が主流です。
店内の照明・グラスの形・煙の演出など、“撮りたくなる瞬間”を設計することが集客のカギ。
見た目を超えた「語れる体験」を提供できれば、シーシャは再びカルチャーの中心に返り咲くでしょう。
注目店舗事例:体験設計の勝ちパターンを探る
Marble Shisha Lounge(新宿):“香り×スイーツ×空間”で共感を生む
香りと甘味のペアリングを前提に設計されたMarbleでは、「煙を吸う」ではなく「香りを味わう」体験を提供。
SNS上では“世界観が完成している店”として拡散が進んでいます。
NORTH VILLAGE:“非喫煙者配慮型”という新たな価値提案
フレーバーの焦げ感を抑え、タバコ感をできるだけ薄めたスタイルが特徴。
“初心者にもやさしいシーシャ”という立ち位置で、口コミ評価が高いです。
健康志向・女性層・非喫煙者を取り込む戦略として成功例と言えます。
渋谷の穴場シーシャ店群:“居心地設計”でファン化を促す
渋谷の小規模店では、あえて派手さを抑えた“隠れ家系ラウンジ”が人気。
照明・座席配置・BGMを緻密にデザインし、「居心地の良さ=ブランド体験」として成立させています。
滞在時間の長さがリピート率の高さにつながる典型例です。
今後の方向性:Z世代が求める“健全なチル文化”とは?
Z世代は「ストレスを癒したいけど、不健康にはなりたくない」世代。
この価値観を踏まえると、シーシャカフェは“健康・安全・映え”を共存させる場所へ進化する必要があります。
- 香り×照明×空間の没入感
- ノンニコチンによる安心感
- SNSで共有したくなるビジュアル性
これらを軸に再構築することで、“チルの民主化”=誰でも楽しめる体験文化を築けます。
オーナー・運営者が今すぐ取り組むべき3つの戦略
① ノンニコチン・代替フレーバーで新客層を開拓
健康リスクを懸念するZ世代に向け、ハーブ・ティーベース・CBD系など代替素材を導入。
「吸う」から「香りを味わう」体験へ転換を。
② SNSと現地体験をつなぐ“UGC連動マーケティング”
来店者が自然に投稿したくなるフォトスポット設計、ハッシュタグ施策、インフルエンサー体験会を実施。
UGCを起点に集客を自動化。
③ コラボ・地域連携で“体験の物語”を育てる
音楽イベント・アート展示・スイーツショップなど、異業種とのコラボで体験価値を拡張。
「ただの喫煙空間」から「文化を共有する場所」へ。
よくある質問(FAQ)
Q1. シーシャの健康リスクはどの程度?
→ ニコチンやタールを含む場合は一定のリスクがありますが、ノンニコチン・ハーブ系では大幅に低減可能です。
Q2. Z世代がシーシャを敬遠する最大の理由は?
→ 「健康不安」「喫煙イメージ」「情報不足」の3つが主因です。
Q3. ノンニコチンシーシャは合法?
→ 日本では合法。ただし、成分表記と販売ルートには注意が必要です。
Q4. 成功しているシーシャ店の共通点は?
→ “空間デザイン×香り×SNS”の三位一体設計を持っています。
Q5. 今後、行政規制は強化される?
→ 換気・年齢確認などの監督は強化傾向。早期対応が信頼構築の鍵です。
Q6. シーシャ業界の未来にチャンスはある?
→ あります。
「香り×体験×ウェルネス」の融合領域で、再成長の可能性が大いにあります。
まとめ:シーシャの未来は“健康と体験の融合”にある
シーシャは単なる嗜好品ではなく、“香りを媒介にしたコミュニケーション体験”です。
Z世代が求めるのは、体にやさしく、感情を動かし、SNSで語りたくなる“体験”そのもの。
淘汰期を迎えた今こそ、「健康 × チル × 世界観」の三要素を融合した“新しいシーシャ文化”を創るタイミングです。
その先にこそ、“シーシャの未来”が広がっています。
✅ 参考リンク:PR TIMES:RECCOO 調査データ(2025年6月)
📩 仕入れ・導入相談は Shisha Amigo へお気軽にご相談ください。