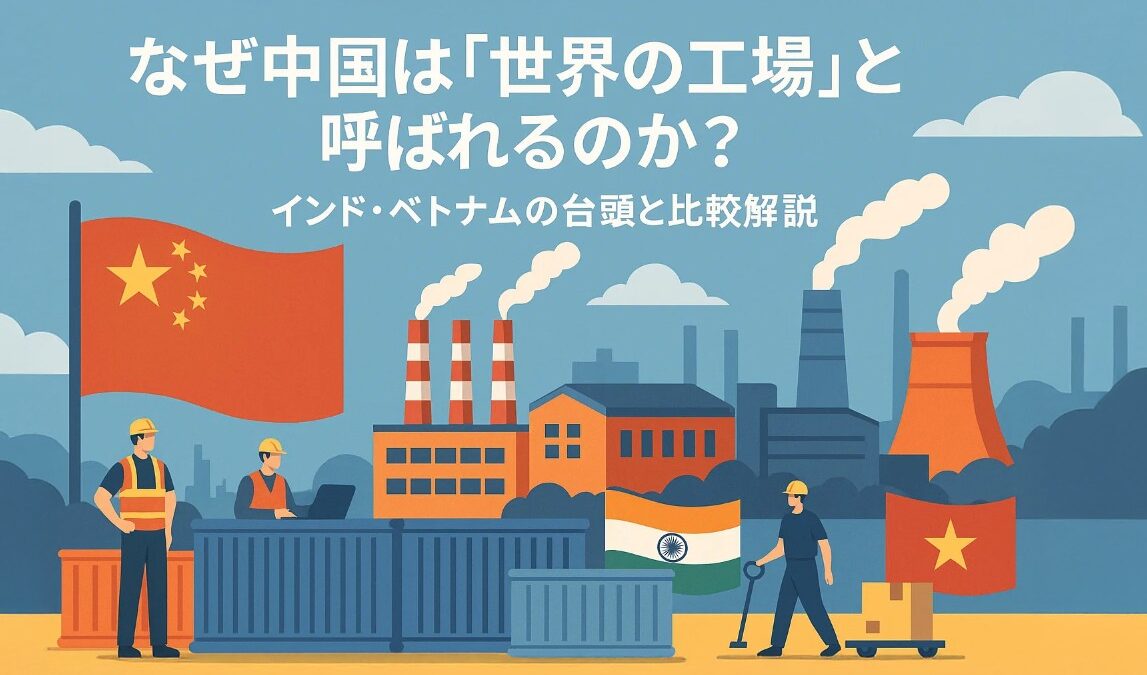シーシャの本体やアクセサリーを含め、多くの製品が「Made in China」として流通しています。
なぜ中国が“世界の工場”と呼ばれるようになったのか?
そして近年「次の工場」として注目されるインドやベトナムは本当に中国に代わり得るのか?
製造業の背景と最新動向を整理します。
中国が「世界の工場」と呼ばれる6つの理由
- 労働力の豊富さと低コスト
14億人の人口規模から製造業に必要な労働力を確保。特に1980〜2000年代は低賃金が欧米企業の進出を後押し。 - 産業集積(クラスター形成)
- 広東省(深圳・広州):電子機器・家電
- 浙江省・福建省:繊維・アパレル
- 江蘇省・上海周辺:化学・機械
部品・素材・人材が近隣で揃う効率性が強み。 - インフラ整備の速さ
上海港や深圳港をはじめとする巨大港湾、鉄道・高速道路網・電力供給が輸出を支える。 - 政府の政策支援
改革開放以降、外資誘致・経済特区・輸出加工区を整備。補助金や税制優遇で企業を呼び込んだ。 - 規模の経済と柔軟性
大量生産で単価を下げられるだけでなく、短納期・小ロットにも対応可能。 - 教育と技能労働者
技術教育を受けた労働者が多く、品質管理やエンジニアリング能力も一定水準に。
👉 単なる「安さ」だけでなく、規模・効率・対応力の総合力で中国は世界をリードしてきました。

中国に代わる候補:インドとベトナム
インド:巨大市場と潜在力
- 成長加速:製造業PMIは2025年夏に過去最高水準を記録。
- 政策支援:「Make in India」「Atmanirbhar Bharat」で外資誘致を推進。
- 労働力:世界最大規模の若年人口が製造業の基盤に。
👉 課題は、官僚的手続き・高関税・規制の不透明さ。外資導入が思うように進まず、製造業比率もGDPの13%程度にとどまっています。
ベトナム:スピードと安定感
- China Plus Oneの成功例:SamsungやIntelが巨大投資を行い、電子・アパレル分野の産業クラスターを形成。
- 政策の安定性:中央集権的な意思決定で、外資対応が迅速。
- インフラ:港湾・工業団地の整備が進み、輸出拠点として信頼性が高い。
👉 課題は市場規模の小ささ。成長余地はあるが、長期的な人口優位ではインドに劣る可能性があります。

インド vs ベトナム 比較表
| 項目 | インド | ベトナム |
|---|---|---|
| 成長スピード | PMI急上昇、GDP成長率高 | 安定成長、外資導入実績豊富 |
| 政策支援 | 「Make in India」など長期構想 | 中央集権型で迅速・実務的 |
| 外資誘致 | 手続きや規制で苦戦 | Samsungなど大型投資を獲得 |
| 投資環境 | 官僚制・高関税が障害 | インフラ整備と政策透明性で有利 |
| 潜在力 | 労働力・市場規模が世界最大級 | 規模は小さいが成熟クラスターあり |
まとめ
- 中国が「世界の工場」と呼ばれるのは、労働力・産業集積・インフラ・政策・スケール・技能が揃ったから。
- インドは潜在力は大きいが、制度的課題が多く「次の世界の工場」としては発展途上。
- ベトナムは規模は小さいが、外資誘致と産業集積のスピードで「中国プラスワン」として強い地位を確立。
👉 製造業の視点で言えば、今後は「中国+ベトナム」や「中国+インド」という分散型のサプライチェーンが現実解になりそうです。
👉 仕入れ・導入相談は Shisha Amigo へお気軽にご相談ください。