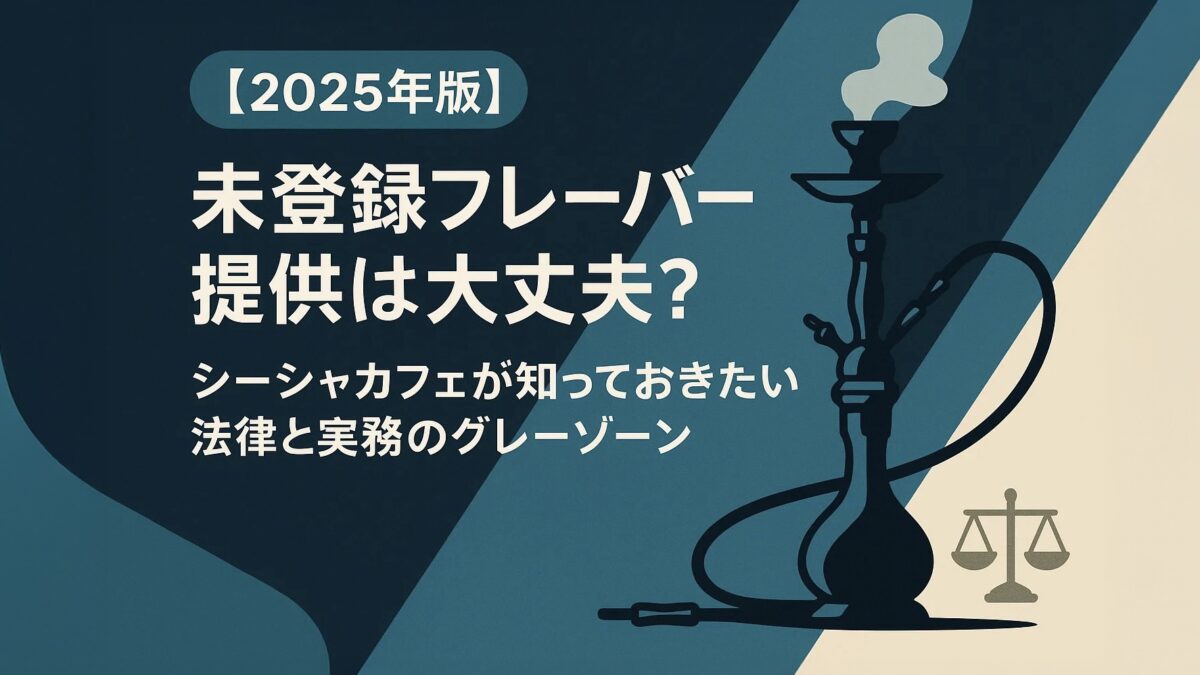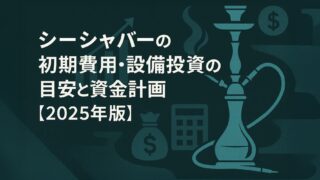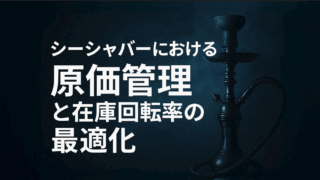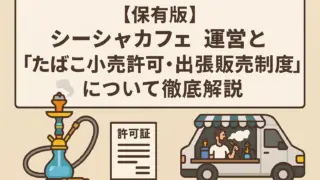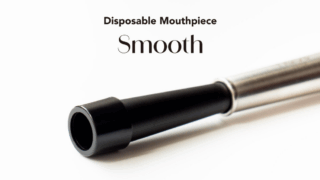1. 法律上の前提
日本におけるシーシャのフレーバー(タバコ葉を含むもの)は、「製造たばこ」に分類されます。
そのため、提供する際には:
- 製造たばこ小売販売業許可を持っていること
- 財務省に登録済みの銘柄であること
が前提条件になります。
つまり、理論上は「財務省に登録されていないフレーバーを提供する」ことは、無許可販売と解釈される余地があるのです。
2. 「販売」と「提供」の違い
現場では、次のようなロジックがよく採用されています。
- 販売:フレーバーをパッケージ単位で売ること
- 提供:シーシャという体験サービスの一部としてフレーバーを使うこと
多くのシーシャバーは、
「フレーバーを単体で売っているのではなく、“席料+サービス料”の一部として提供している」
という位置づけをしています。
この考え方によって、理論上のリスクを回避しているのが実務上の実態です。

3. 実務上のグレーゾーン
実際には、多数のシーシャバーが未登録フレーバーを提供しています。
その背景には:
- 財務省の登録制度が追いつかず、海外の新ブランドがすぐに登録されない
- 「提供=販売ではない」というロジックが広く浸透している
- 行政による積極的な摘発がほとんど行われていない(黙認に近い)
結果として、現場では「未登録フレーバーを使うのが当たり前」という状況になっています。
4. なぜリスクがあるのか?
ここで重要なのは、「実務では普通に行われていること」=「法的に安全」ではないという点です。
法解釈上のグレー
- たばこ事業法は「販売」を規制対象にしていますが、「提供」が完全に除外されているわけではありません。
- 行政が「提供=販売」と解釈すれば、摘発の対象になり得ます。
実務上の安全性が担保されていない
- 多くの店舗で提供されていることは、合法の証明にはなりません。
- もし健康被害や未成年利用などの問題が発生した場合、「未登録フレーバーを提供していた」事実は確実に指摘されます。
行政裁量で変わる
- 現状は黙認でも、今後の規制強化で一気に「違法扱い」とされる可能性があります。
- 電子タバコや加熱式タバコでも、わずか数年でルールが大きく変わった前例があります。
5. ⚠️ SNSでの「吊し上げ」問題
近年、一部のSNSや掲示板では「未登録フレーバーを提供している=違法だ」と断定し、シーシャバーを名指しで批判する“自警団的アカウント”も見受けられます。
しかし実際には:
- 未登録フレーバー=即違法と決まっているわけではなく、あくまでグレーゾーン
- 行政による摘発や公式見解がない限り、違法と断定するのは難しい
- 「提供」と「販売」は法的に区別されており、単純に「販売禁止=提供も禁止」とは言えない
そのため、SNSで一方的に「NG」と決めつけて吊し上げるのは正確性を欠いた行為です。
むしろ、業界やユーザーに不必要な不安を広げるだけのリスクもあります。
👉 本当に重要なのは「業界全体が正しい知識を共有し、リスクを理解したうえで行動すること」であり、
批判よりも情報共有と透明性が求められます。
6. 安全な選択肢とは?
リスクを最小化するなら、財務省登録済みのフレーバーを仕入れて提供することが最も安全です。
現場の実情としては未登録フレーバーが多数派であるものの、法解釈上のリスクをゼロにできるのは登録済みフレーバーのみです。
長期的に安定経営を目指すなら、登録済みフレーバーを中心に据えつつ、新ブランド導入は慎重に検討する戦略が賢明です。
まとめ|「今はOK」でも将来は分からない
- 理論上:未登録フレーバー提供は違法リスクを含む。
- 実務上:多くの店舗で提供され、黙認状態に近い。
- SNS批判:一方的に「違法」と決めつけるのは誤りであり、正しくはグレーゾーン。
- リスクの本質:規制強化や行政判断で状況が一変する可能性がある。
👉 シーシャカフェのオーナーやスタッフは、
「現状のメリット」と「将来のリスク」の両方を理解し、バランスの取れた仕入れと経営判断を行うことが重要です。
👉 仕入れや導入相談は Shisha Amigo へ