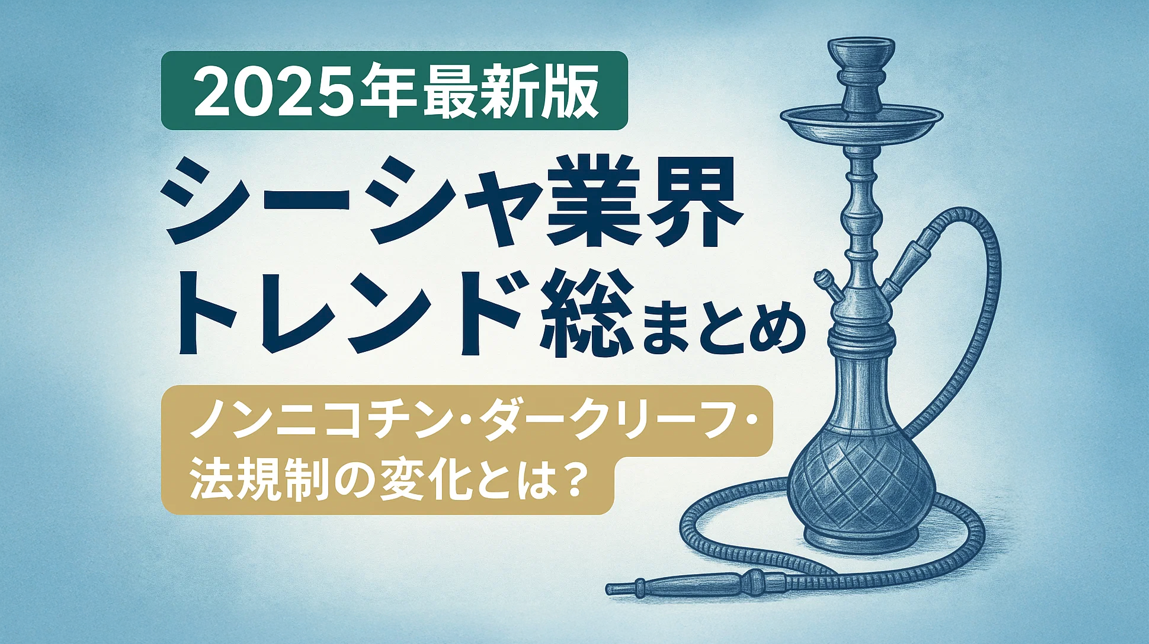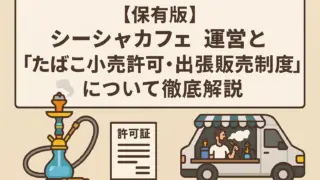1.シーシャ市場の現状(〜2024年)
急成長期: 2022年春の調査では全国に約1,013店のシーシャ提供店があり、そのうち東京都は368店で2位の大阪府(106店)の3倍以上。
都内のシーシャ店数は381店のスターバックスに迫り、353店のマクドナルドを上回る。
全47都道府県に最低1店が存在し、関東・近畿を中心に急増している。
人気の背景: アンティーク調の器具やカラフルな煙の“映え”が若年層のSNSで話題となり、女性やタバコを吸わない層まで取り込んでいる。
料金はシーシャ1台1,500〜2,000円でチャージ・ドリンクを含め2,500〜3,000円が相場。
健康志向の高まり: フレーバーの多様化が進み、ニコチン・タールゼロのノンニコチン製品やCBDを含むフレーバーが登場。
これによりタバコを吸わない客層にも門戸が開かれた。
2.2025年の注目トレンド
2.1 ヘルシー志向とノンニコチン市場
- ノンニコチンの定番・デクラウド: デクラウド(Decloud)は本物の果実やオーガニックシロップだけを原料にしたノンニコチン・ノンタール・無添加フレーバーで、濃厚な煙とジューシーな風味が楽しめる。白ぶどうやジャスミンなど女性人気の高い味が多く、タバコを吸わない人でも満足できると日本のシーシャカフェで人気を集めている。厚い煙を求めるユーザーが「ニコチンなしでも満足できる」「使いやすい」と評価することが、ノンニコチン市場でデクラウドが“ほぼ一強”になっている理由とされる。
- 健康志向の広がり: 2025年は国産・無添加のフレーバー開発が進み、CBDや漢方素材を組み合わせた「吸ってリラックス・美容」系の製品も増える見込み。新規ユーザーや女性層の取り込みにつながるため、各店がこの分野に注力している。
2.2 ダークリーフの人気拡大
- ダークリーフとは? シーシャ用タバコ葉を洗わずに製造するためニコチンが非常に多く、強いキック感と濃厚な味が特徴。タングジアーズ(Tangiers)などが有名で、熱管理が難しいため上級者向けだが、重めの煙を好む愛好家に支持されている。
- 流行の背景: 2024年以降、ダークリーフを扱う店が増え、専門家や愛好家向けの勉強会が開催されている。例えばEGG SHISHAでは2024年から2025年にかけてダークリーフやシガーリーフの研究会を開催し、最新フレーバーの試煙やセッティング方法を共有している。2024年の試煙会ではDarkSideのコーラやMust Haveのミルキーライスといったダークリーフ系フレーバーが特に人気だった。
2.3 地方・観光地への拡大
- 都市圏に集中していたシーシャバーが地方都市や観光地へ広がり始めている。空き店舗対策として誘致する自治体や、外国人観光客向けにシーシャ体験を提供する宿泊施設が増えつつある。インバウンド需要の回復もあり、ホテルラウンジや温泉地にシーシャ体験コーナーを設ける動きが進むと予測される。
2.4 コラボレーションとイベント
- シーシャと他業種の複合店舗(カフェ+シーシャ、クラブ+シーシャなど)が増加。音楽フェスやアートイベントにシーシャブースを設置するなど、非日常的な空間演出ツールとして活用されている。
- シーシャ×サウナなどの体験型イベントも開催され、新しいチル文化を生み出している。
2.5 ブランディングと専門性の向上
- 店舗乱立の結果「どこも同じ」という状態になりつつあり、2025年以降は量から質への転換が進む。フレーバーをむやみに増やすより、看板メニューを磨き上げ、空間や接客を含めた満足度を高めることが重要視される。
- スタッフの専門性(フレーバーミックスや機材知識)を高めることが差別化要因となり、「フレーバーソムリエ」的な人材が評価されるようになる。
3.法制度・許認可のポイント
・合法性と年齢制限: シーシャはパイプ用タバコの一種であり、適切な小売販売許可を得れば合法。しかし日本の法律では喫煙具の所持・使用は20歳以上に限られており、シーシャ専門店への入店も20歳未満は禁止される。
・ノンニコチンでも要許可: Decloudなどニコチンフリーのフレーバーであっても、シーシャ器具自体がタバコ製品とされるため未成年は利用不可であり、店舗側はたばこ小売販売業許可もしくは出張販売許可を取得する必要がある。
・規制強化の動き: 国内で未登録フレーバーの提供や無許可営業が問題となっており、2025年に向けて財務省や関係機関が監視を強化する可能性がある。適法な仕入れルートの確保と許可の明確化が経営者の責務となる。
4.シーシャバー経営者様へのアドバイス
・フレーバー数より満足度: 看板フレーバーを決め、常にベストな状態で提供する。空間づくりや音楽・照明にも投資し、総合的な体験価値を高める。
・パーソナライズされた接客: 来店・注文履歴を管理し、個々の好みに合わせた提案を行う。SNSやアンケートを通じて顧客の声を反映する。
・法令順守と仕入れ管理: 許可手続きや仕入れ先の適法性を確認し、国の認可を受けたフレーバーのみを扱う。深夜営業や防火管理など関連法規も遵守する。
・専門知識と人材育成: スタッフへの研修を充実させ、フレーバーブランドや機材の知識、ミックス技術を磨く。サービス向上に向けたモチベーション施策も検討する。
5.まとめ
シーシャ業界は2024年まで「店舗数を増やす」段階にあり、2025年以降は健康志向・体験価値・専門性が鍵となる成熟期に入る。
ダークリーフなどコア層向けの重い味わいが注目される一方で、デクラウドに代表されるノンニコチンのフルーツフレーバーが若年層や女性に支持され、ヘルシー志向が市場を拡大している。
規制や許認可の厳格化も進む中、各店は法令順守と独自のブランドづくりに注力し、質で選ばれる時代に備えることが求められる。